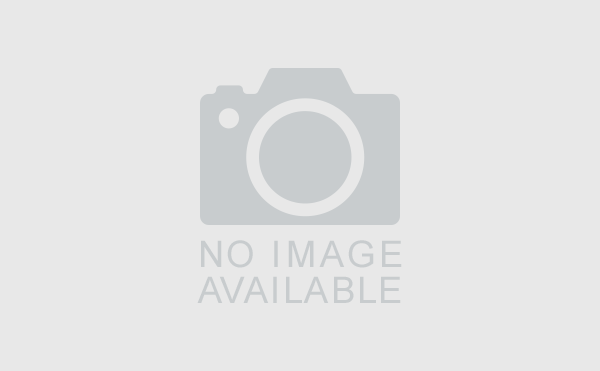ヴォーカルアンサンブルEST 第32回演奏会
昨年に第31回演奏会に引き続き、今回もVocal Ensemble ESTの演奏会に行ってきました。三重県に行くのは久しぶりと思いきや、四日市市にちょいと用事があったので1週間もしないうちにまたやってきました。
到着しました。ESTの演奏会楽しみです。 pic.twitter.com/RKbfNg0u06
— イマッチ@作曲・編曲サービス始めました (@imatch0603) November 2, 2025
客席に入ると、最前列は亀山少年少女合唱団・久居少年少女合唱団・Suzuka 西部少年少女合唱団の子供たちと、暁高等学校合唱部、香良洲自動車学校の5団体で、また横の座席もEST用で割り当てられていました。意外と座席が少ないようにも思いましたが、後ろのほうは空いていたのですぐ座ることができました。私が入ってきた時は客席から見て左側が埋まっていて、なぜか右手側はそこそこ空いていました。真ん中が埋まるのはわかるのですが、ここまで偏りがでるとは思いませんでしたね。
ちなみにプロジェクターで歌詞が表示されていましたが、見えづらかったので結局わかりませんでした。
第1ステージ【生誕500年記念】パレストリーナの夢
毎年宗教曲から入るというイメージですが、今回もまた宗教曲からのスタートです。声に透明感があって、ESTの特徴に合っていると感じました。まるで教会で聴いているかのような印象ですね。
Sicut cervus
パレストリーナの曲を挙げるとしたらまずこれが出てきますね。私はそこまで合唱曲に詳しいわけではありませんが、詳しくない私でも第一にこれが出てきます。無難に終わった印象でしょう。可もなく不可もなく、最初の曲としては全く文句ありません。
Denn er hat seinen Engeln befohlen
メンデルスゾーンの曲で少人数の混声4部合唱(重唱?)ですね。Bassがもう少し重厚感があればよかったのですが、今回は全体的に声が軽めなんでしょうね。この曲だけでなく、全体的に低音はもう少し響きが欲しいとは思いましたが、声が軽いのならどうしようもありません。これも和音の響きは悪くありません。
Super flumina Babylonis
またパレストリーナに戻ります。この曲はもの悲しさが出ていますね。ほどよい緊張感がありました。最後は5度の和音で終わっていたので、それも緊張感を増している要因でしょう。
II. Tota pulchra es(グレゴリオ聖歌の主題による4つのモテットより)
今度はデュルフレ(Dulrufle)の女声合唱。異世界の感じがする響きでしたね。高温も難なく出しているように見せるのは本当に難しいです。かなり自然に入ってきました。素晴らしいです。最後のアルトも男声的な感じで終わっていてよかったです。
PETRUS
一言でいえば現代音楽ですね。短2度を主体として和音を作るので、あまり宗教曲らしさを感じません。パレストリーナみたいに旋律を掛け合うようにするのかと思いきや、縦をそろえる感じです。
最初は不穏な感じでしたが、「Alleluja」からは穏やかに終わりましたね。
第2ステージ【まなざしの行方】
曲ごとのつながりを意識している印象でした。まなざしというか表情や感情を表していますね。
ESTI DAL
コダーイもよく聞きますね。「夕べの祈り」という意味ですが、男声合唱だけどやわらかく包み込まれる印象でした。穏やかな表情を表しているでしょう。一日が終わるタイミングで穏やかにあとは寝るだけ。私の勝手な印象です。
まじめな顔つき
三善晃の「クレーの絵本第2集」の一曲です。曲調はまじめではありません(笑)。タランテラ的なリズムで軽やかに進みますね。これもまた軽やかさを表現できていましたね。
あと、ESTI DALから続いているかのように錯覚しました。これも狙って構成を考えているのでしょうね。
Even When He Is Silent
ここでまたゆっくり目な曲です。穏やかな感じの曲調なんですが、神様が沈黙していても、「私は愛を信じる(I believe love)」と何度も強く表現していましたね。後で説明文を読んだのですが、神様が沈黙する、つまり神様でさえもお手上げな状況であっても絶望に負けないという意味合いを持っているのでしょう。「I believe love」の繰り返しというのはそういうことでしょう。
無伴奏二重混声合唱のためのカンタータ「人間の顔」より
プーランクの混声合唱組曲ですね。この人数で2群で合唱をやるのはなかなか挑戦的でしたが、すんなりと聴くことができました。
Vl. Le jour m’etonne et la nuit me fait peur
悲しい雰囲気の曲です。プーランクにしてはかなり控えめな曲だと思います。恐怖を表現してるからそこまで感情が出ないということでしょうか。演奏も控えめな感じでよかったです。
VII. La menace sous le ciel rouge
「La menace」の入りがやっぱりプーランクだと感じましたね。不穏さを常に感じさせるのが聴いていていいですね。やっぱプーランクはこうでなければなりませんね。
VIII. Liberte
祈りのような曲でしたね。自由を希望する曲でしょう。これこそ2群合唱の真骨頂でしたね。しっかり重厚感が出ていました。最後らへんのソプラノのhigh C(C6)を難なくやっているのは私には想像を絶するところでしょう。調子よくいくと本当に音楽が進んでいきますよね。第2ステージの終わりとして素晴らしいです。
第3ステージ【みやけまつり】
10分の休憩が終わり、今回の演奏会のテーマ「みやけまつり」です!ビラやチケットの「みやけまつり」の文字、どうやって組み合わせているかわかりますか?音符や強弱記号、ト音記号やヘ音記号などを組み合わせて文字にしています。ここに工夫が凝らされていると、演奏会に足を運んだ甲斐があります。
亀山少年少女合唱団・久居少年少女合唱団・Suzuka 西部少年少女合唱団
亀山市と鈴鹿市から遠路はるばる来ていますね。ちなみに久居はもともと市の一つだったんですが、2006年の合併で津市に吸収されました。今は津市久居〇〇町のようにかつての市の名前が残されていますね。と脱線していましたが、3団体合同でも意外と舞台は余裕があるんですね。こどもたちだからというのもあるのでしょうが。今回は「のはらうた1」より3曲を披露してくれました。
はるがきた
ナレーションは自然な感じでよかったです。ここで無理に感情をこめたがる子たちが多いですが、普通にしゃべってくれるだけでいいです。小ネタも要りません。すぐ曲に入ってくれるほうがいいですね。
児童合唱団らしく軽やかさ明るさを全面的に押し出していましたね。こういう演奏がいいんですよ。
よるのにおい
最初ドビュッシーの「月の光」と思いましたが、絶対狙って作曲してるでしょ。というか私も作曲・編曲する際は、クラシックの曲の一部を採用することはありますね。油断してると眠りそうですね。ところどころ月の光が入って来るので、余計に眠気を誘います。まあ、眠りませんでしたがww
ぼくはぼく
ちょっと寂しい曲調ですよね。でも「ぼく」がわからなくなりそうだけど、ちゃんと見失わずに済んだのでしょうか?なんか考えさせられる詩でしたね。子供には難しい言葉でしょうが、音楽を通して触れる機会ができたのはよかったでしょう。私も正直この歌詞の意味があまり理解できていません。見失うことはよくありますからね。でも、戻ってくれば結果オーライでしょう。
暁高等学校合唱部
今度は高校生の部です。「ひとめぐり」という曲もまた考えさせられる詩ですね。
曲調は明るいのですが、人間の死をテーマに取り扱っているので、暗いのか明るいのかよくわからない曲です。死ぬことを明るく考えると言うと語弊がありますが、誰でも人生の終着点にたどり着くのだからしょうがないという意味合いもあるのでしょう。壮大な演奏を聴かせてもらいましたね。高校生でこのレベルはなかなか出せないと思います。
高校生だからこそこういう重たいテーマを扱っているのでしょう。高校生の時点で家族が亡くなるという経験って、ある人とない人で大きく分かれるでしょう。まだ現実味がないかもしれません。私ぐらいの年齢(33歳)になると祖父母が亡くなるということはあるのでしょうが、親が亡くなる経験をしている人はあまりいないでしょう。いろいろ考えさせられますね。
香良洲自動車学校
ここに行っても自動車の教習を受けさせてくれるわけではないようです(笑)。れっきとした合唱団ですのでご注意を。ちなみに香良洲町は久居市とともに、2006年の合併で津市に吸収されました。香良洲海岸もありまして、農業や漁業、海苔の養殖などの産業が盛んです。合唱団は主に四日市市が活動拠点だそうです。いろいろ間違えそう。ここの演奏初めて聴きましたね。
混声合唱とピアノのための「遠きものへーー」より3曲目の「おやすみなさい」は、油断していると眠ってしまいそうですね。どれだけ眠らせようとしてるのかが伝わってきます。まあ、私は眠りませんでしたが(2回目)。睡眠不足だったら間違いなく眠っていますね。それぐらい心地のよい演奏でした。
ヴォーカルアンサンブルEST
ここで作曲者の三宅悠太さんと、指揮者の向井正雄さんがご挨拶をしていました。いつもだったら、最初で向井さんがあいさつするはずなのに変だなあと思っていました。
ESTは委嘱作品、金子みすゞの死による混声合唱曲集「まなざしのむこう」Iを一部初演で演奏しました。まだ完成版ではないそうです。来年でようやく完成する予定ですね。なかなか途中経過で演奏を見せるというのはあまりないかと思われます。1曲だけ披露するのならたまに聴きますが、この形は初めてですね。
1. 灰
無伴奏の曲です。ソロから始まり団員が少しずつ入場していく形です。あの横側の席に座れなかった理由がこの曲にあります。横の座席からも入場して徐々に全員がそろっていく形ですね。
2度の和音が中心だったので、終始張りつめた印象でした。
2. 金平糖の夢
本当に金平糖を矢継ぎ早に食べたら甘すぎて胃もたれしそうですね。夢に現れてもお断りしたいぐらいですw
曲調は金平糖らしくdolceです。演奏は胃もたれしませんでしたww
3. 金魚のお墓
ピアノの高音部はグロッケンシュピールみたいな音色でしたね。軽やかに金魚の最期を看取って、土に埋めて供養する感じでしょうか。可燃ごみに捨てられてもおかしくはないでしょうが、ちゃんと供養してもらえてよかったでしょう。ピアノという楽器がグロッケンシュピールとハープのように聞こえましたね。優しい音色が金魚をちゃんと供養する様子を表しているのでしょう。
4. あらしの夜
雷が鳴り続いている間に、大雨が降っては止んで振っては止んでというのを表現しているようでした。これは止んでいても油断できない感じでしょう。ちなみに止んでいる間に傘を持たずに歩くと大雨になります。そう、持っていないときに限って大雨はやってきます。逆に傘を持てば降らずに終わるかもしれません。そんな感じの夜でしょう。
5. みえない星
星は無数にあるけれど大体見えないんです。あまりにも遠すぎるので。見えないものにも意味があるのでしょう。
ここからは私のイメージですが「あらしの夜」からのAttacaと考えると、雲はまだ残っていて、月や星を見ることはできないでしょう。でも、そんな夜もまた悪くはないですね。雲があっても星はなくなりません。ただ見えないだけです。見えないから存在しないと結論付けるのは暴論ですね。でも残念なことに、その考え方のほうが広まりつつありますね。
最後はG majorで終わるのかと思いきや、F majorの上にG majorを重ねると言う幻想的な終わり方でした。なかなか意表を突かれた形です。私の作曲・編曲ではこういう終わり方をしないので面白いですね。
ワンステージメンバーとともに
ステージ最後はESTメンバーのほかに、ワンステージメンバーも一緒になって歌っていました。
星めぐりの歌
宮沢賢治の作詞・作曲だそうです。最初作詞だけだと思っていました。夜になにもせずに空を眺めて聴いていたい曲ですね。ショパンのノクターンとはまた違った楽しみ方ができそうです。特にお酒も飲まずに聴いていたい感じです。林光編曲もまた優しい曲調ですので、そちらも是非とも聴いてみてください。どちらも心が浄化されるような曲調ですね。
音楽の木
この「音楽の木」は初めて聴きましたね。有名なのはなかにしあかね作曲のほうですが、このバージョンもよかったです。夜に気にもたれかかって音楽を聴いている様子がうかがえます。
学ぶ
「頭でっかちになって、物事の本質を見失っていないか?」という谷川俊太郎からのメッセージかもしれません。大地に学ぶことがたくさんありますね。あまりにも自然とかけ離れたことをしていると、大きなしっぺ返しをくらうかもしれません。教科書にあることだけではなく、自然はいろいろ教えてくれます。農業や林業、漁業をやっている人のほうが、大学の教授よりも詳しいのは一目瞭然でしょう。机上の理論も必要かもしれませんが、それだけでは意味がないということです。私たちへの戒めかもしれません。
アンコール
演奏会の最後を締めるのは立原道造の詩から「子守歌」ですね。また寝かそうとしていますね。どれだけ寝させようとしたら気が済むのかww
この曲もまた優しく歌いかけるので、油断していると眠りますね。まあ、私は起きていましたが(3回目)。
ちなみにロビーコールは木下牧子の「鴎」です。懐かしかったです。ついつい歌いそうになりましたが、さすがに観客として楽しむべきなので歌うのは慎みました。初心を忘れない意味でも鴎はいいですね。
最後に
今回もESTの演奏会に来てよかったですね。欲を言えばバスの重厚感が欲しかったですが、声質の都合があるのでこればかりはどうしようもありません。来年の委嘱初演は完成版になるでしょうが、ぜひとも楽しみにしています。
昨年と一緒で、行きは江戸橋駅から歩いて、帰りは津駅で特急ひのとりで帰りました。特急ひのとりに乗りながら飲むビールはおいしかったです。